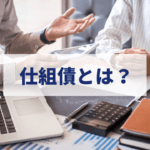株式に投資をするなら、財務情報などから将来有望な企業や安定して長生きできる企業を選び出さなければなりません。そのために役立つ指標の一つが、PERです。
この記事ではPERとは何か、どんな風に使って株式を選べば良いのかなどを解説していきます。見た目がよく似ている「PBR」にも触れ、違いも見ていきましょう。
この記事を読んで銘柄選びのスキルを上げて、株式投資の成功に一歩近づきましょう。
この記事の目次
PERとはどんな指標?
PER(Price Earnings Ratio)とは「株価収益率」のことで、1株あたりの純利益に対する株価の大きさを示す指標です。株価は市場が評価する企業価値を反映しているので、PERは利益の大きさに対して過大評価されているか、過小評価されているかを表しています。
PERが低い銘柄は、利益の大きさの割に株価が安いということなので、市場で割安に放置されていることになります。このような銘柄を割安株と言い、市場の評価が適切になれば株価が上がると考えられるので、投資家に人気があります。
反対にPERが高い銘柄は、利益の大きさに対して株価が高く、市場が割高な評価を与えていることになります。AIや自動運転など将来有望なテーマに関連する企業など、高い期待を寄せられている企業の株式はPERが高く割高なことが多いです。
PERは株価が異なる銘柄の比較に役立つ

PERは、株価が割安かどうかを判断できる指標の一つです。銘柄分析の難しさは銘柄によって株価が異なることが一因ですが、PERを使えば株価が異なる銘柄を1つの基準で比較することができます。
株Aも株Bも株価が1000円の場合、株価が同じなので利益が大きい方が「たくさん稼いでいる企業」と言えます。1株あたりの純利益(EPS)を比較し、一般的にはEPSが大きい方が投資価値が高いと考えられます。
しかし、株価もEPSも違う2つの銘柄を比べる場合はどうしたら良いのでしょうか。このような場合にPERが役立つので、以下の2つの銘柄を例に計算してみましょう。
- 株A:株価が1000円でEPSが100円
- 株C:株価が1500円でEPSが120円
1株あたりの純利益(EPS)が、株Aは100円、株Bは120円だった場合、PERは次のように計算できます。
- 株AのPER=1000÷100=10倍
- 株CのPER=1500÷120=12.5倍
株AのPERは10倍、株CのPER12.5倍で、株Aの方がPERが低いことが分かりました。したがって、株Aの方が割安、株Cの方が割高と考えることができます。株価やEPSが違う銘柄でも、PERを使えば同じ基準で割安か割高かを比較することができるのです。
よく似たPBRとの違い
PERとよく似た指標に、PBR(Price Book-value Ratio)があります。これは「株価純資産倍率」という指標で、PERと同様に株式が割安かどうかを判断するために使う指標の一つです。PERは利益、PBRは資産に注目した指標です。
PBRは、1株あたりの純資産に対する株価を表しています。PBRが1倍の場合、市場における株価の評価と、実際に企業が保有している純資産とが等しく釣り合っている状態です。1倍より大きければ純資産に対して株価が高く、1倍より小さければ純資産に対して株価が安い状態になっています。
すなわち、PBRが1倍よりも小さい場合、その銘柄は割安と考えられます。PERを見るときに併せてPBRも確認し、割安株を絞り込むと良いでしょう。
PERの目安はどれくらい?

日本企業の場合、PERの平均は15倍と言われています。一般的に、15倍より低い銘柄は「割安株」と呼ばれています。平均より割安な銘柄を探すなら、PERの目安は10倍以下とするのが良いでしょう。
ただし、業界や業種によって平均的なPERは異なります。せっかく10倍以下の割安株を見つけた!と思っても、その業界では標準的なPERかもしれません。
例えば、銀行などの金融機関はPERが低めなので、10倍を下回っていることが多く、10倍程度では割安株とは言えません。一方、製造業のPERは20倍を超えている銘柄も多く、15倍でも低い方と言えることがあります。
このように、業界によってPERの水準には違いがあります。同業他社のPERも見てその業界のPERの目安を調べた上で、より割安な銘柄を探すのが良いでしょう。
PERを利用した株式の売買

株式投資で儲ける方法の一つが、「株式を安いときに買って高くなったら売る」方法があります。しかし、買い時・売り時が難しくて悩んでいる初心者投資家の方も多いのではないでしょうか。
買い時・売り時の目安になるのがPERです。この項目では以下のステップでPERを利用した売買について解説していくので、ご参考ください。
- PERが低い銘柄を買う
- 株価が上がるのを待つ
- PERが上昇したら売る
PERが低い銘柄を買う
これから株価が上がりそうな銘柄として、まずPERが低い銘柄を探して購入します。業界平均と比べて低PERの銘柄を購入しましょう。
もちろん、購入する前にはPER以外にも確認するべきことがあります。直近の業績や配当、チャートの形を見て、今後も株価が上がっていくと予想できる銘柄にのみ投資をしましょう。「業績が悪くなっているみたい」などのネガティブな材料がある場合、株価が下がっていく可能性が高いので、PERが低い銘柄でも投資をしてはいけません。
株価が上がるのを待つ
割安な株を購入できたら、しばらく放置しておきます。その銘柄に対する市場の評価が適切な水準に戻ってくれば、自然と株価は上がっていきます。
もし一向に株価が変わらないか下落している場合は、銘柄選びに間違いがあった可能性が高いです。損切りと思って売却し、銘柄選びに戻りましょう。
PERが上昇したら売る
割安株を買えたら、自然と株価が上がってきます。株価の上昇とともにPERも上昇するので、「割安株」から「適切なPERの株」に変化していきます。業界平均と同じくらいのPERになったら売り時と考えられます。
例えば、PERが10倍のときに買った銘柄は、市場での評価が見直されれば株価が上昇し、PERは15倍くらいまで上がってきます。業界平均くらいまで上がったら、それ以上の伸びは高望みせず、売却してしまうのが良いでしょう。その後も株価が上がって割高な評価を得られるかどうかは予想しにくいからです。
このように、PERが低い状態から適切な水準に戻る自然な動きを利用すれば、株式の買い時・売り時に迷いにくくなります。他にも不確定な要素が多いので確実に上手く儲かるとは言えないのですが、売買の目安になるので、PERを参考に使ってください。
PERで株式を選ぶときの注意点
PERが低い銘柄には、「割安な状態で放置されている理由」があります。割安株を見つけたからといってすぐに買うのではなく、なぜ安いのか調べる癖をつけましょう。理由に納得でき、それでも将来有望だと考えられるなら買いと言えるでしょう。
割安株を見つけたら、最低でも「営業利益が増加しているか」は確認しましょう。営業利益が減少している場合、企業に投資するだけの魅力が無くてPERが低くなっているのかもしれません。業績が良いかどうかを手っ取り早く知るために、必ず営業利益は確認してください。
まとめ

PERの意味やPERを活用した投資術などについて解説してきました。業界によって異なりますが、日本企業のPERの平均は15倍程度なので、10倍以下の銘柄は割安株の目安となります。
PERは銘柄分析や買い時・売り時の判断に役立つ指標です。
どんな銘柄を買ったら良いのか分からない、株式を買ったもののいつ売れば良いのか分からない、など悩んでいる初心者の方には、特に強い味方になってくれるでしょう。
株式投資セミナーでは、難しい投資用語や指標、実際のトレード方法などが学べます。セミナーのテーマはさまざまで、超初心者向けのものから、現在取引をしていて良い結果が出てないとお悩みの投資経験者の方向けの内容もあります。
株を学びたいと思ったら、ぜひ活用してみてください。